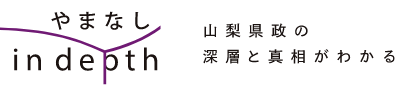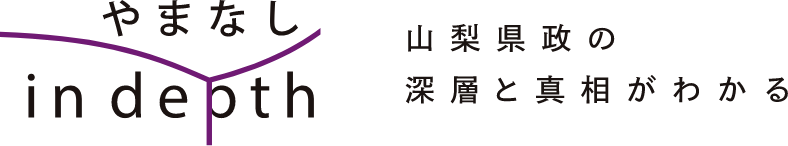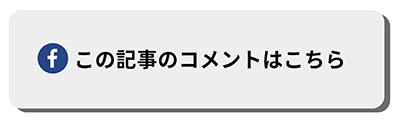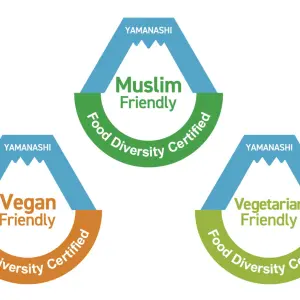空港のない山梨に、“アートの空港”をつくる ミライの街に必要なものをトコトン追求
アートが嫌いな人…たぶんいない。
美術館やコンサートに頻繁に行かなくても、好きな絵や音楽はきっとあるはず。
県が進める富士五湖自然首都圏構想は、アートを応援している。
河口湖で暮らす、ちょっと変わったアーティストたちが山梨県とともにめざすミライのまち構想。
目次
富士山が見える非日常空間 “6okken”
車が1台やっと通れる登り坂を進み、河口湖を望む高台に出た。ここに、アーティストが創作活動をしながら生活するアーティスト・ラン・レジデンス“6okken(ロッケン)”がある。その名のとおり、6棟のコテージが横並びに建つ。
目の前に富士山がドーンと構える絶景に、「富士山をこんなに近くで見られるなんて、非日常ですよね」と言うのは、6okkenを立ち上げ、運営する今野誠二郎さん。自身も「筒|tsu-tsu」の名義で活動するアーティストで、『Forbes JAPAN(フォーブスジャパン)』の「世界を変える30歳未満30人 アート部門」に選ばれたひとりだ。
大学に通いながら、東京・神楽坂でアトリエを兼ねたシェアハウスを運営していたが、若いアーティストを支援するオーナーから「山梨県で芸術家たちが集まる場をつくらないか」と提案されたのをきっかけに、初めて河口湖を訪れた。
今野さんは「はじめは山梨県と言われてもピンとこなかった」と言うが、ためしに来てみると「ここでやりたい」と直感的に感じるものがあったという。
決め手となったのは、富士山を間近に眺める唯一無二の景色があること。そして、東京へのアクセスの良さ。徒歩15分のバス停から2時間バスに乗ると、新宿駅南口の「バスタ新宿」に到着する。
2022年の夏、今野さんは東京から河口湖に移住した。現在は今野さんを含む4人のアーティストが6okkenで暮らしている。

ミライの街に必要なもの…それがアート
「“フォーブスの30人”に選ばれた若者たちが、河口湖に移住してアーティスト活動をしているらしい」という話は、山梨県庁にも届いていた。
県職員の石田幸司さんは、「6okkenの活動に可能性を感じた」という。
山梨県は、富士五湖地域の自然や景観を守りながら、観光地と都市機能をあわせもつミライのまちづくり構想を進めている。その名も「富士五湖自然首都圏」構想。
企業や教育機関だけでなく、社会起業家やNPOなど幅広い人たちでつくる「富士五湖自然首都圏フォーラム」が2022年に発足し、「国内最高のリゾート地 × 最先端の首都機能 = 世界に類を見ない先進的な地域」をめざし、議論を深めている。
※詳しくはこちら
5月には、フォーラムから派生した国際コンソーシアム「富士五湖グローバル・ビレッジ」が社会課題の解決をテーマにしたアートの国際巡回展を開催した。
ミライのまちは、単なる都市機能の充実が求められるだけではない。
そう、大事な要素のひとつが、アートなのだ。
石田さんは学生時代に訪れたヨーロッパで見た光景をイメージしていた。近所のおじさんがふらっとクラシックコンサートを聴きに行ったり、道端で遊んでいる子どもたちが絵画に詳しかったり。「こんなに身近にアートがあるなんて!」と衝撃を受けた経験がある。
みんなが日常的に芸術に触れることで、山梨からプロ・アマ問わず作品が生み出されるような環境をつくるためには、どうしたらいいのか。
そんなとき、今野さんと出会った。
「芸術が一部の人だけの敷居の高いものになってしまっては意味がありません。人々の心や生活にアートが溶け込んでいる地域づくりを、6okkenに住む若いアーティストたちと一緒にめざしたい」(石田)
「積み上げるのが生活、削ぎ落すのが制作」
アーティストの生活とはどのようなものなのか。
今野さんは18歳から役者を志し、映像や演劇を経て、演技を用いたパフォーマンスアーティストになった。ある実在の人物を取材・インタビューし、その人が憑依したかのように演じていく過程を公開する“ドキュメンタリーアクティング”という独自の表現手法で作品を手がけ、6okkenを運営する“今野誠二郎”と、アーティスト“筒|tsu-tsu”の2役をその時々で使い分けている。
「アーティスト活動には刺激の多い東京の方がいいのでは?」と尋ねると、今野さんはそうではないと言う。
東京は出会う人の数は多いが、タイムパフォーマンスが重視されコミュニケーションが希薄になる。
「6okkenはコンビニまで歩いて50分かかります。だから、ここに来た人は腰を据えて滞在するしかない。共有する時間が長いぶん、アーティスト同士がお互いのことを深く理解しようとするし、人生を支え合う仲間ができます」(今野)
自然の中に身を置き、仲間と語り合う日々。他人とともに生きていくとはどういうことか、表現とどう向き合えばいいのか、を考える時間も増えたという。今野さんが好きな言葉があるという。
「積み上げるのが生活、削ぎ落すのが制作」
表現は日々の暮らしの積み重ねから、ダイヤを削り出すように生まれてくる。そうであれば、「なにを積み上げるか」から考えなければいけないというのだ。
彼が定義する“アーティスト”とは、音楽家や画家だけをさすものではない。「その人が手放せば、この世からなくなってしまう視点に向き合い続ける態度」を持つ人をアーティストと呼び、彼はそれを可能にする環境を作っていると繰り返した。
“インターコレクティブ”のレシピを広めたい
今後は6okkenをモデルケースにして、アーティストのための生活共同体(コレクティブ)の作り方を発信しようとしている。
「2021年から山梨県が『やまなしメディア芸術アワード』を設立するなど旗振り役になってくれています。こうした追い風を受けつつ、北杜や西湖や富士吉田など各地に点在している文化拠点と連携して、みんなで活動していく地盤をつくりたい」(今野)
アーティストが自主的に運営する生活拠点を増やして、つなげる。“インターコレクティブ”という新しい発想だ。
しかし、課題もある。富士五湖の地域の人たちに6okkenの存在はあまり認識されていない。富士五湖周辺は飲食店などが少なく、移住してきたアーティストたちが地元住民と交流できる場がない。
「もっと地域を巻き込みたい」という今野さんに、石田さんとともに自然首都圏構想を担当する平賀亮太さんと入倉健人さんも思いを同じくする。
「構想の一環として、県が6okkenの活動を後押しすることで、アートを地域に還元できるのではと考えました」(平賀)
昨年10月から担当になった入倉さんも「前向きな活動を支援できるのは嬉しい」と意欲的だ。

世界唯一の合宿型芸術祭「ダイロッカン」
今年3月には6okken主催の芸術祭「ダイロッカン」が1か月間にわたり開催された。
前半のシンポジウムでは山梨周辺の文化芸術関係者や東京のギャラリー関係者、人類学の研究者などが集まって、「なぜいま山梨なのか」「なぜこのような生活拠点が必要なのか」を議論。国内外から集まった18人のアーティストが6okkenで約2週間の合宿を行い、3月30日、31日に最終的な成果をパフォーマンスやワークショップなどで一般公開した。
※詳しくは6okkenのインスタグラム
県は富士五湖自然首都圏フォーラムの活動支援として、活動費の4分の3を補助(上限300万円)している。
「県の制度を活用して、初の海外アーティストを招待することができました」(今野)

山梨をアートの空港にする
今野さんの夢は、山梨県だけにとどまらない。
「山梨をアーティストの空港のような場所にしたいんです」
海外から山梨にアーティストがやって来る、そして山梨からも日本のアーティストが世界に挑戦していく――。そんなエコシステム。
「今野さんの“山梨をアートの空港にする”という発想が、我々のモヤモヤした思いをスッキリと言語化してくれた。6okkenの取り組みが自然首都圏構想のコンセプトとクロスしているので、アートの力で社会がどう変化してくのか期待が膨らみます」(石田)
共通するのは、山梨ならではの芸術祭にしたいという思いだ。有名なアートフェスティバルの後追いは絶対にしたくないと今野さんは言う。
「SNSの“いいね”の数だけを指標にしていると、本質を見失ってしまう。6okkenに来たアーティストが1、2年後に山梨に戻ってきてくれたり、山梨のアーティストが海外に挑戦したりするきっかけになれば、それは自信をもって成果だと言えますよね」
目先のインプレッションで測れない、100年先を見据えた地域づくりが、まずアートの世界から始まっている。
文・北島あや、写真・今村拓馬