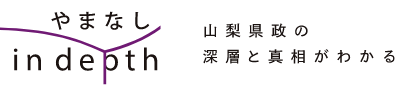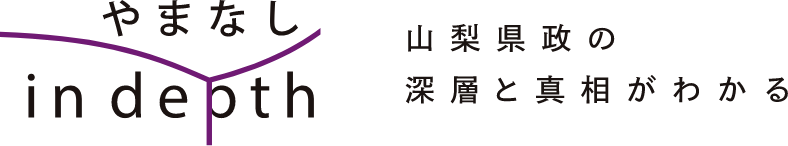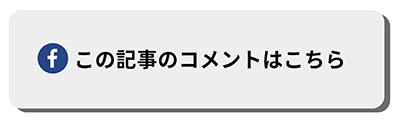大規模山火事を食い止めた消防団、激闘の335時間
県内で社会のためにがんばっている人たちがいる。
その1人1人に光を当てる企画が始まります。
第一回目は、地域の安全を守る「消防団」のみなさんです。
消防団員は地域の防災活動に取り組む有志の市民によって構成されていますが、日々訓練を重ね、火災が起これば急行して消火活動にあたります。
2025年1月に大蔵経寺山の大規模火災が発生したときも、懸命に働く彼らの姿がありました。
現場の最前線で火を食い止めた、団員たちの姿をフィーチャーします。

2025年度から、新コーナー「in depth プラス」を始めます。
登場するのは、皆さんの身近で活躍するミライ思考の人たち。幅広い人たちにじっくり話を聞き、その息吹をお伝えします。
■この記事でわかること
✔ 登山道もない山上での出火。消防団員らは斜面に階段を作るところから消火作業を始めた
✔ 自衛隊ヘリの活動に合わせ、消防団員らは登山、下山を繰り返した
✔ 消防団共通の悩みは定員の確保。だが、近年は女性団員も活躍する
■おすすめ記事
・「もし富士山が噴火したら、うちの技術が役立つ」企業を大募集!火山のプロたちが選んだのは……
・地方の声が国を動かした! 山梨発の「活火山法改正」
・ドローンパトロールで人の命も樹海も救え
出火!
2025年1月18日土曜日、13時24分に笛吹市消防本部に119番通報が入った。笛吹市と甲府市にまたがる大蔵経寺山の山頂から1、2本の煙が上がっていた。笛吹市側からの出火だった。
その時、笛吹市消防団団長の水上兼一さんは自宅の窓から山を見ていた。

水上:どんどん燃え広がって、これは長くかかりそうだと覚悟しました。

消防署の指令課から各分団長に一斉メールが送信された。まず火災発生地点に近い春日居分団と石和分団に招集がかかり、現地指揮本部が設置された笛吹市春日居スポーツ広場に83人の消防団員が駆け付けた。
山火事は風の向きや気象状況であっという間に燃え広がる。同じ頃にアメリカのロサンゼルスでは大規模な山火事が発生し、多くの人的被害や家屋が焼失するという最悪の事態に陥っていた。
そうなる前に、なんとしても食い止めなければならない。
ボランティアで構成される消防団は、基本的に消防本部と同じ活動を行う。消防本部の人数には限りがあるため、山火事のような大規模災害時には消防団の力がなくてはならない。

水上:昔の消防団員は自営業が多かったのですが、最近はほとんどがサラリーマンです。土曜日の昼間でしたが、休日の人も、仕事中の人も、火事の知らせを聞いてすぐに集まってくれた。「自分は消防団なんだ」という責任感が強いんです。
15年前にも起きた山火事
一方、甲府市消防団でも第1次出動として甲運分団、里垣分団、玉諸分団、東と南の方面隊長が集結していた。
現場に向かった甲府市消防団団長の川手謙吾さんは、15年前にも起きた大蔵経寺山の山火事を思い出していた。当時、笛吹側の火が風に煽られて甲府方面に燃え広がってきたからだ。


川手:夕方の風が西から東に吹いていて、明日になれば甲府の方まで火が回ってしまうと焦りました。笛吹の水上団長は子どもの頃から知っている仲間なので、無茶なことだと思いつつ会って開口一番に「頼むから今日中に消してくれよ」と言いました。
しかし、その日は日没が近づいていたため、消防団は入山できなかった。夜になると山の尾根が甲府側まで真っ赤に燃えていた。
過酷すぎる、消火活動の最前線
翌日、笛吹市と甲府市の両側から消火活動が始まった。

水上:笛吹市側の山には消火栓がない。団員たちは山の頂上まで人力で水を運ぶしかありませんでした。
そこで、リュック型の水嚢から水を噴射する「ジェットシューター」を活用することにした。しかし、作戦は一筋縄ではいかなかった。

水上:火元まで行く登山道がないため、斜面に土嚢と石を並べて、階段をつくるところから始めました。2000ℓの水槽車から各ジェットシューターに水を汲んで、軽トラで運べるのは麓まで。そこから先は20ℓ弱の水を入れたジェットシューターを背負い、山を登らなければなりません。笛吹市消防団が持っているジェットシューターは75基しかないので、登れるのは80人程度が限界です。全員でこの作業を2往復しました。
一方、甲府市側では三石付近のキャンプ場に消火栓があった。山の中腹まで1.2㎞の道のりにホースを引き、山中に設置したビニール製の水槽に水を溜める作戦だ。

川手: 45度の斜面にロープを張って、急こう配の岩場を登りました。少し触っただけで石が落ちてくるので、ホースを担いで運び上げるのは危険と隣り合わせの作業です。1月でしたが、防水衣の中は汗ダクでした。慣れない現場で体調不良になる人もいたので、第一目標は団員が怪我をしないことでした。

19日、「長崎知事が陸上自衛隊に災害派遣を要請した」と連絡が入った。まもなくヘリコプターが飛んできて空中放水を始めるという。団員たちはすぐさま作業を中断して下山した。
テレビの映像では小さなバケツをひっくり返しているように見えるかもしれないが、ヘリコプターの放水量は約5000ℓにもなる。大量の水を一気に落とすため、ヘリが来ると山から人を退避させる必要がある。

水上:ヘリコプターでの放水がなければ山火事のような大災害には太刀打ちできません。ありがたい存在です。
しかし同時に、現場を指揮する団長たちには悩みもあった。
ヘリコプターの飛行は気象状況に大きく左右されるため、到着時間を正確に把握することが難しい。ヘリの飛行状況は刻々と変化し、そのたびに消防団員は山を登ったり下りたりしなければならなかった。

水上:団員たちから「いつ山に行けるのか」と聞かれても答えられないし、待ってもらうしかないのが一番つらかった。みんな消火活動する気満々で来てくれているので、待機している団員たちの視線が痛かったですね。
残り火をつぶす
その後も諦めずに自衛隊ヘリが飛んできては、空中放水を繰り返した。その合間を縫うように、消防団員たちは地道に山の消火活動を続けた。

22日、大きく火災が広がっている箇所は火を消すことができた。それに伴い、ヘリの出動要請が終了したと団員に伝えられた。
しかし、消防団の仕事はここからが正念場だった。堆積した枯草や石の下には小さな火種が無数に残っていた。再燃すれば大きな火災が発生してしまう。

水上:人海戦術で草木をかき分けながら、煙っているところにジェットシューターで水をかけていく。

川手:消防本部や自衛隊と共に、「今日中に残り火を全部消すぞ!」と士気を高めて臨みました。
その後も消火活動は続き、1月27日金曜日に鎮圧。2月1日土曜日に再燃の恐れがないと確認され、笛吹市消防本部から鎮火が報告された。
2人の消防団長は15日間の激闘を振り返った。

水上:山火事による人的被害や家屋の消失は1件もありませんでした。危険な現場でしたが、消防団の誰も怪我することなく任務を遂行することができたのは、日頃の訓練が実を結んだからだと思います。

川手:消防団員たちはみんな、自分たちの地域を守るという意識を持っている。みんなが自分の持ち場を素早く理解して連携プレーしたからこそ、山火事の現場で慌てることなく動くことができました。
記事に登場する消防団員の素顔は
 置かれていた法被とヘルメット
置かれていた法被とヘルメット
家業で看板屋を営む水上兼一さんは、笛吹市消防団に入って23年だ。先輩たちに入団を勧められて入団を決意した。「帰ったら玄関に法被とヘルメットが置いてあった。みんな昔はそんな感じでしたよ」と笑う。30歳の息子も消防団に入っている。「消防本部からメールで火災現場の地図が送られてくると、僕より早く飛び出していきます」と次の世代に期待を滲ませる。
 1週間予約キャンセル
1週間予約キャンセル
甲府市消防団に入団して27年になる川手謙吾さんは整体師だ。今回の消火活動のために、入っていた整体の予約を1週間キャンセルした。15年前の山火事で家の裏山が燃えた経験があるため、お客さんたちも予約をずらすなど協力してくれたという。「大人になってからの仲間が増えるのはめちゃくちゃ楽しいですよ。やめたいと思ったことはない」と断言する。
 夜なべ仕事の板金塗装
夜なべ仕事の板金塗装
団員たちの安全管理を担った甲府市消防団東方面隊長の高野義行さんは入団して24年だ。普段は板金塗装の仕事をしているが、山火事が起きてから昼間は消防団にかかりきりに。納品日に間に合わせるため、夜なべ仕事で対応した。「いつ火事があっても、家族が行ってこいと言ってくれる。家族の理解がなければ、こんなに長くは続いていないと思います」。
昔とイメージ変わっても減少傾向に
地域の安全を守るために、最前線で任務にあたる消防団員たち。しかし近年は、地域住民との温度差を感じているという。山火事に向かう自衛隊ヘリの音がうるさいという声もあった。
高野さんは「火災予防週間で消防車を動かしているときに『ご苦労様です』と言われるとやりがいを感じる。我々の活動に、少しでも寄り添ってもらえるとうれしいです」と話す。

さらに消防団員の数も減少している。甲府市の団員定数は1333人だが、令和6年度が1007人、令和7年度が992人となり、若者の“消防団離れ”が加速する。この問題に県内すべての分団が頭を悩ませている。
「昔のように男たちが夜通し酒を飲んでいるイメージがあるかもしれませんが、いまはまったく違います。懇親会を開催する程度で、強制されることもありません」と消防団の人たちは口を揃える。
一番大きく変わったのは、女性団員が活躍していることだ。
娘がやりがいを見つけた場所
4年前、高村なぎささんが甲府市消防団に入団したのは23歳のときだった。きっかけは消防団に所属していた幼馴染の母親から「一緒に入らない?」と誘われたことだった。
現時点で消防団の女性は25人いる。そのうち東分団の女性団員は3人だったが、1人欠員が出たためスカウトされたのだ。
「小さいころから父の背中を見ていたから、消防に興味があったので入ってみようかなと思ったんです」
なぎささんの父は東分団長を務める興津秀弘さんだ。32歳で入団し、現在52歳。消防団に20年間所属している。
興津さんは、なぎささんから入団の話を聞いたとき「正直、困ったなと思った。周りと馴染めるのか心配でした」と振り返る。しかし、なぎささんがいると場が明るくなり、すぐに団員たちになくてはならない存在になった。
「人間関係が難しそうなイメージがありましたが、実際に入ってみると年上の人たちがみんな可愛がってくれました。横のつながりができるし、地元の人たちと仲良くなれるので楽しいです」(なぎささん)

消防団員の活動は多い。地震に対応する非常招集訓練、無線の通信訓練、地域イベントや祭りの警備、火災予防週間や年末年始のパトロールなど、各分団によって内容も様々だ。
さらに、夏季はモモやブドウなど果樹園の盗難対策として夜間パトロールも行っている。6月から8月頃まで、だいたい21時~23時頃に果樹園を見回る。
父と娘で一緒に夜間パトロールに行くこともある。そんな姿に影響されてか、なぎささんの夫も2年前に「僕もやってみようかな」と“軽い気持ちで”入団した。
これまで興津さんはあまり娘に消防団の話をしてこなかったが、今は家族が集まると自然に消防の話題になるという。
去年、なぎささんは年1回開催されるポンプ操法大会に出場した。ポンプ車や小型ポンプの技術を競う大会で、号令をかける役目を担った。1ヵ月半の間、仕事が終わると週2、3回の練習に欠かさず参加した。
興津さんは「一生懸命やってくれるからありがたい。娘の頑張りでうちの分団が評価されることもあります」と誇らしげだ。
一方で、なぎささんは「父は今回の山火事でも最前線で活動しましたが、私はまだ実践の経験がありません」と悩みをこぼす。
なぎささんが「もうちょっと訓練を増やした方がいいかな?」と父に小声で聞く顔は真剣そのものだ。
「もともとボランティアが好きだったこともあり、消防団にどっぷりハマっちゃいました。今後、大災害が起きたときに自分はちゃんと動けるのかという不安はありますが、いざというときに備えて訓練していきたい」(なぎささん)
消防団は「地域を守る責任感」と「人とのつながり」受け継いでいる。女性も若者も、誰もが自分らしく活躍できる場がここにある。

文・北島あや、写真・今村拓馬